日本酒は、あなたにどんなイメージを抱いていますか?
ビールやワインとは異なる大人の味わい、強いアルコール度数、そして知識がないと理解しづらい…。多くの方が日本酒に対してさまざまな印象を持っているかもしれません。
しかし、日本酒はその多様性と深い魅力によって、数多くのファンに愛されています。辛口から甘口まで、さまざまな味わいが楽しめるだけでなく、日本酒の歴史や製造工程も興味深いものです。
本記事では、日本酒の種類やそれぞれの特徴、基本的な飲み方、そして日本酒の歴史を丁寧に解説していきます。
初めての方にもわかりやすく、日本酒を楽しむためのヒントを提供します。
また、これから日本酒デビューを考えている方にも役立つ情報をお届けします👍
日本酒の世界へと足を踏み入れ、未知の味わいや文化に触れる旅に出かけましょう!

(この記事は2019年11月22日に公開後、2023年7月31日に追記し再公開しました。)
Contents
日本酒ってどんなお酒?日本酒の種類
まず初めに日本酒とは…?というところからご説明します。
日本酒の深い歴史も一緒に辿っていくと、飲む前からワクワクしてきますよ🍶
日本酒の種類を楽しむためには、辛口・甘口・香りなどを意識して選ぶことも重要です。それぞれの特徴を知ってから飲むと、日本酒の風味を今まで以上に堪能することが出来ます。
日本酒とは?覚えて損なし!日本酒の基本

日本酒は米・麹・水というシンプルな原料で作られた文字通り日本独自のお酒で一般的に「清酒」と呼ばれています。
酒税法の下、清酒はアルコール22度未満で次の要件が備わっているものと決められています。
- 米・米麹及び水を原料として発酵させ濾したもの
- 米・米麹・水・及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発行して、濾したもの
- 清酒に清酒かすを加えて濾したもの

日本酒の種類 「辛口」と「甘口」とは?

さらに日本酒は突き詰めていくと、同じ銘柄の日本酒でも複数種類があるのにお気づきになると思います。
日本酒には様々な種類と特徴があります。日本酒は大きく分けると「辛口」と「甘口」の2タイプがあります。
味の違いはよくアルコール度数によるものと勘違いされがちですが、日本酒の種類はアルコール度数ではなく『日本酒度』によって変わります。度数が高いから辛口というわけではないのです。
日本酒度とは日本酒の比重を表すもので、糖分が少なくなるほど「辛口」に、糖分が多くなるほど「甘口」の日本酒になります。
辛口の日本酒は冷たい「冷酒」や、特にお酒好きの方に人気です。
甘口の日本酒にはワインのような味わいを楽しめるものから、スウィートで軽快な味わいまでさまざまです。
よく聞く日本酒「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」って何?
日本酒の「純米酒」や「大吟醸」(だいぎんじょう)「本醸造酒」(ほんじょうぞうしゅ)なんて言葉を耳にしたことが皆さんも一度はあるかと思います。
これらの種類が決まるのには二つのポイントが挙げられます。
原材料で決まる「純米酒」
まず一つ目のポイントは「純米酒」かどうか。
どういうことかご説明すると、最初にお話しした通り日本酒は基本的に米・米麹・水から作られています。米・米麹・水のみを原料にしてつくられる日本酒が「純米酒」です。
味のバランスを整えるため「醸造アルコール」
日本酒には味のバランスを整えるため「醸造アルコール」という原料を添加しているものがあります。
この醸造アルコールは香りを豊かにし、味わいもすっきりと辛口に仕上げてくれるだけでなく、品質も安定させてくれるという優れものです。
お米を磨く「精米歩合」

さらにもう一つのポイントは原料の米をどのくらい削っているのかということです。
日本酒造りにはある程度まで削った(精米した)米を使います。
この削り具合を精米歩合と呼ぶのですが、この「精米歩合」によっても種類が変わってきます。
例えば、「精米歩合40%」という表記のあるお酒は、米の60%を削って残りの40%で仕上げたお酒という意味です。

ちなみに余談ですが、私たちが普段食べている白米は精米歩合は約90%なので、玄米から10%ほどしか削っていない状態なんです🍚(筆者は初めて知りました…)
日本酒造りにおいて米を削ることは、米の中心に近い部分を使うことができ、雑味のないすっきり爽やかな味に仕上がると言われています。
これらの「原材料」「精米歩合」が日本酒を見極めるには大きな手掛かりになります。
「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」とは
米・米麹・水だけでつくられるのが「純米酒」
日本古来の酒。精米歩合による規定はなし。濃厚な味のものが多く、原料米の精白度の高低によって味に違いが出る。固有の香味と色沢が良好。
米・米麹・水に醸造アルコールを加えたもので精米歩合が60%以下
こうじ米使用歩合が15%以上が『吟醸酒』
米・米麹・水に醸造アルコールを加えたもので精米歩合が70%以下
こうじ米使用歩合が15%以上が『本醸造酒』
原料米1トンあたり、120リットル以下の醸造用アルコールを添加した酒。
日本酒の特定名称酒の表示として認められているのは「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」「大吟醸酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」「特別純米酒」「特別本醸造酒」の8種類です。
それ以外の日本酒は「普通酒」「一般酒」と呼ばれています。
日本酒の種類 特定名称酒一覧
日本酒の特定名称酒8種類の区分を表にまとめました。
原材料が【米・米麹・水】のみ
| 特定名称酒 | 使用原料 | 精米歩合 | 特徴 |
純米大吟醸酒 | 米 米麹 水 | 50%以下 | 高価なものが多く、固有の香味と色沢が特に良好 |
| 純米吟醸酒 | 米 米麹 水 | 60%以下 | 特別純米酒と同じ精米歩合が義務付けられており、酒質に差が無いものもある。固有の香味と色沢が特に良好 |
| 特別純米酒 | 米 米麹 水 | 60%以下または特別な製造方法 | 原材料の種類によって酒質に違いがでる。固有の香味と色沢が良好 |
原材料に【米・米麹・水・醸造アルコール】を使用したもの
| 特定名称酒 | 使用原料 | 精米歩合 | 特徴 |
| 吟醸酒 | 米 米麹 水 醸造アルコール | 60%以下 | 固有の香味と色沢が良好。大吟醸と同じで醸造アルコール添加量は少ない |
| 大吟醸酒 | 米 米麹 水 醸造アルコール | 50%以下 | 固有の香味と色沢が良好。醸造アルコールを添加量は少なく、発酵中の酵母に影響を与えて美味しい酒造りを行うために添加している |
| 本醸造酒 | 米 米麹 水 醸造アルコール | 70%以下 | 原料米1トンあたり、120リットル以下の醸造用アルコールを添加した酒 |
| 特別本醸造酒 | 米 米麹 水 醸造アルコール | 60%以下または特別な製造方法 | 醸造アルコールを添加していることがわかるような酒も中にはある。香味と色沢が特に良好 |
日本酒の味と香りの違い
さらに日本酒は香りと味で4つのタイプにも分類されます。
・薫酒(くんしゅ)
フルーティーな果実や花の香りが特徴の日本酒。「大吟醸」など吟醸系が当てはまり、若い女性にも大人気のタイプ。
・爽酒(そうしゅ)
日本酒の中でも最も口当たりが軽く、すっきり爽やかな味。普通酒や本醸造が該当し淡麗(口当たりがさっぱりとしていて癖がなく、糖度と酸味の低いもの。)辛口タイプ。
・ 醇酒(じゅんしゅ)
お米の旨味やコクを感じるタイプで、純米系の日本酒が該当。どっしりとしていて、味付けの濃い料理にも◎
・熟酒(じゅくしゅ)
古酒や熟成酒が当てはまる。ドライフルーツやスパイスのような香りとまったりとした飲み口のタイプ。

さらには貯蔵期間の長さでも新酒・古酒・長期貯蔵酒と分けられます。
ここまで一気に日本酒の種類をご紹介してきたので、頭がこんがらがってしまいそうですがご安心ください。
最初はあまりよくわからなくてもお店の人に聞いたり、ラベルを見ていくうちに少しずつ日本酒の種類や特徴が掴めてくるはずです。
日本酒デビューはまず美味しく感じることが一番大切なので、肩の力を抜いていきましょう☺
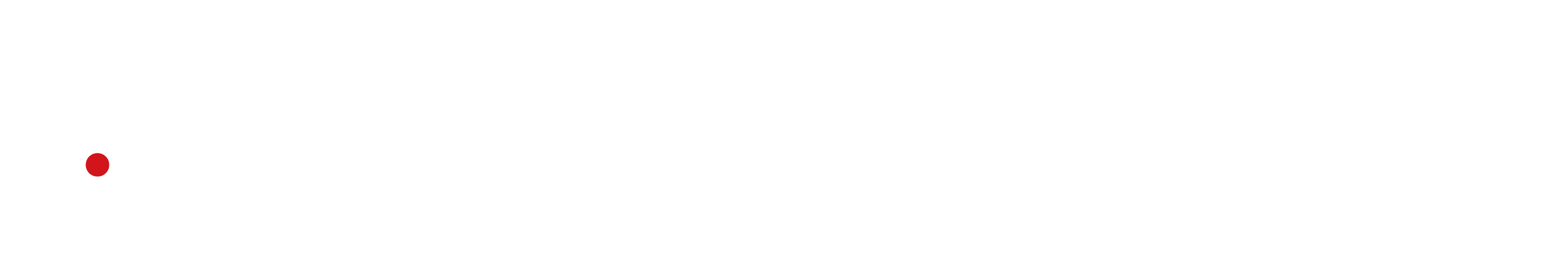




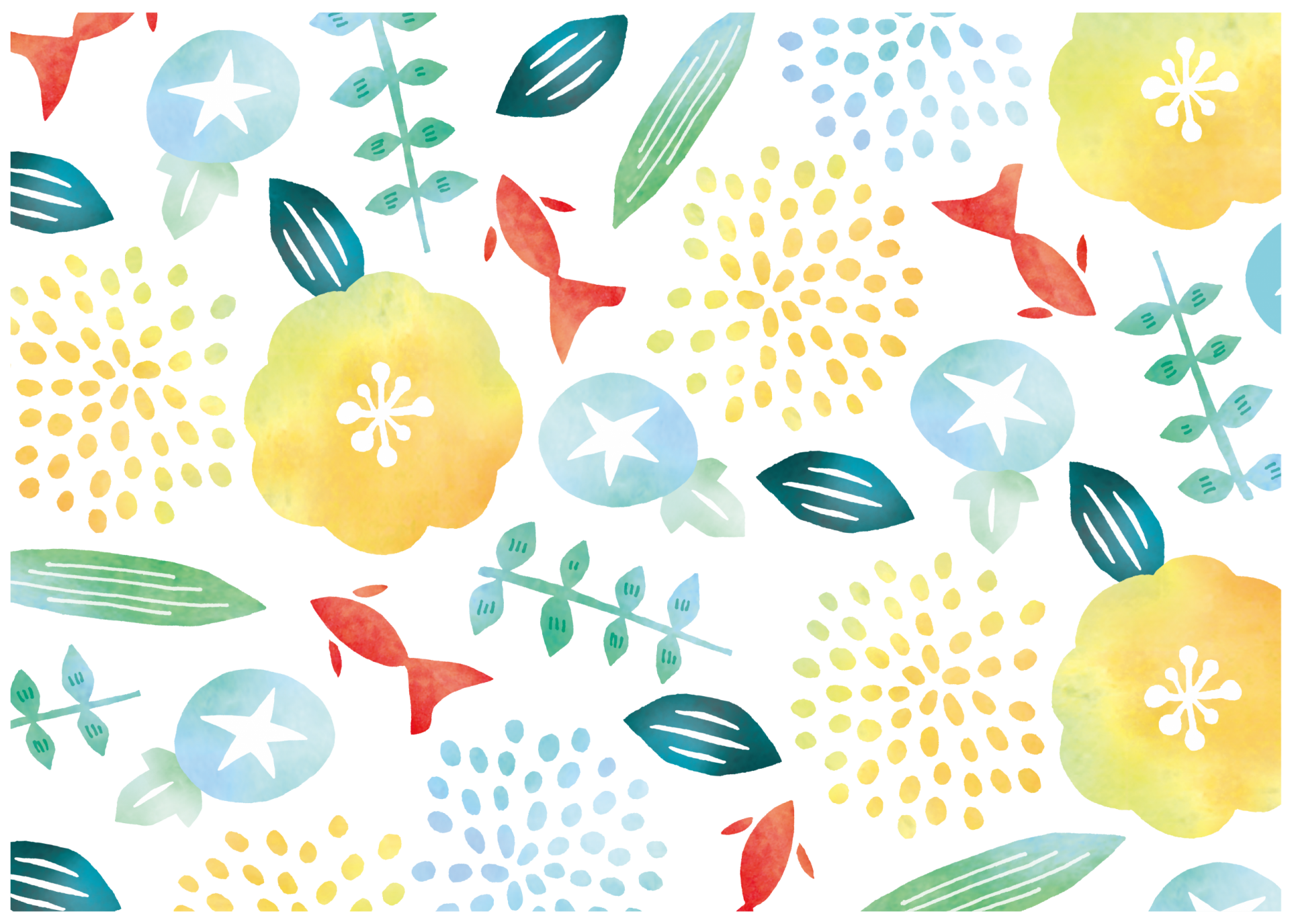


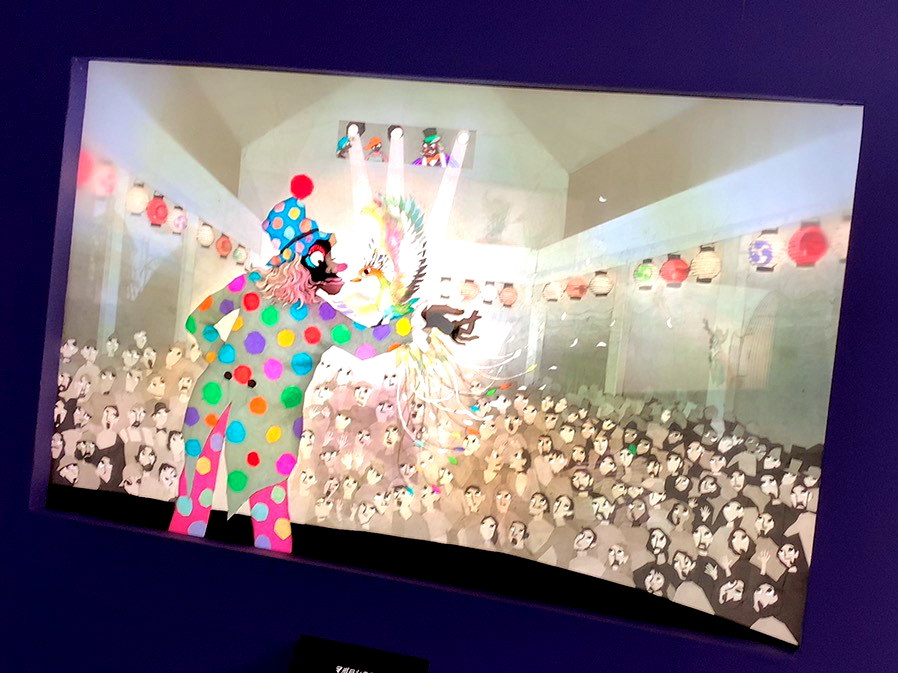





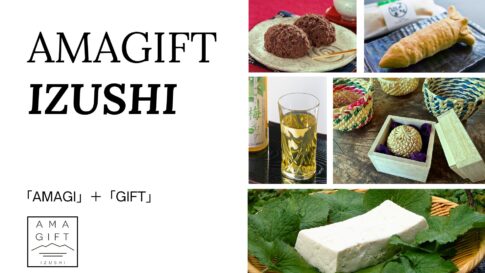


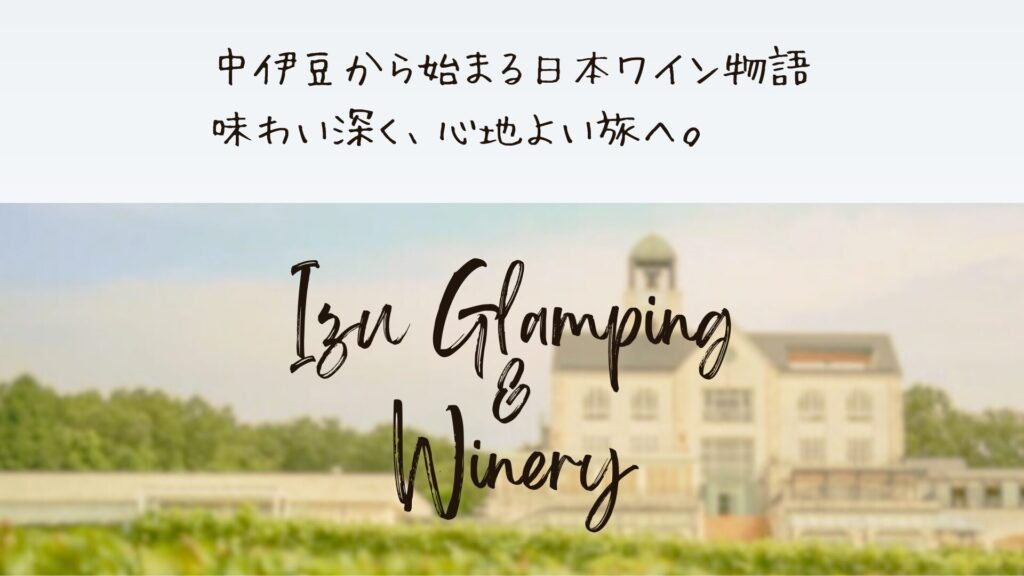
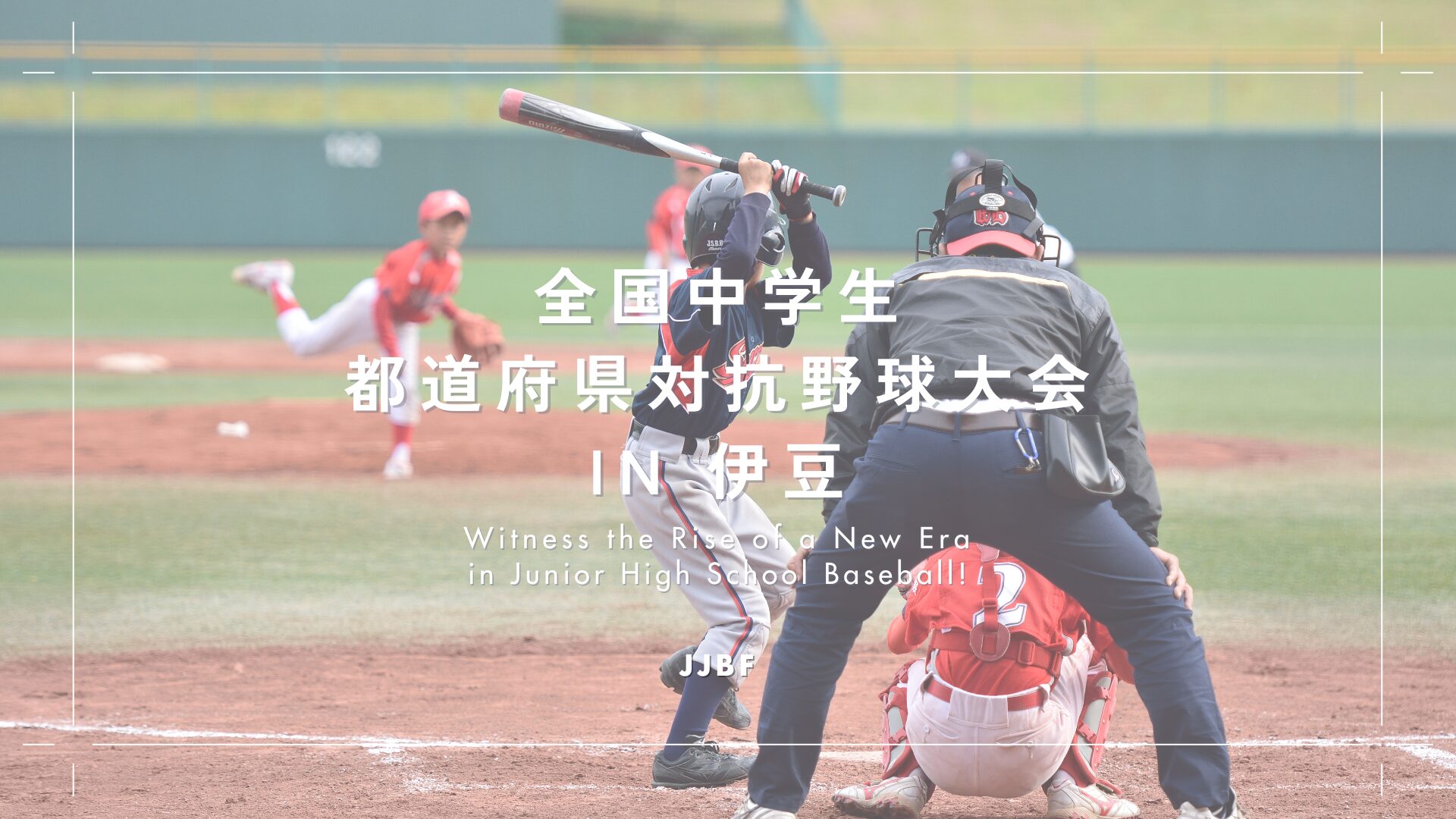

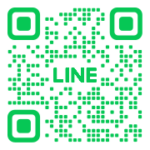
コメントを残す